|
2002年9月議会 |
| 文化行政 『研究機関としての博物館について』 | ||
|---|---|---|
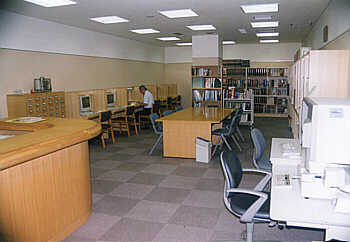 質問 宮岡治郎
質問 宮岡治郎① 茶の博物館として、全国的に見て、どの位置にあるか。 ② 『茶』に関して、どのような内容の質問が多いのか。 ③ 収集された資料で、収蔵庫が飽和状態とならないか。 ④ 学芸研究は、厳格な実証主義に徹すべきものか。 ⑤ 研究者の主体性や特技は、充分に発揮されるか。 ⑥ 研究内容の社会的な有用性を、どの程度考慮するか。 ⑦ 好事家的な来館者の要求に、どのように対応するか。 ⑧ 入間市地域の近代の歴史は、先進的で内容も豊富であると考えるが、研究対象としての魅力はどうか。 答弁 生涯学習部長 ① 青少年が学習体験等を通じ、夢や豊かな心を育みながら、生きる力を身に付けていける社会教育施設として再構築する。 ② 常設展示場の茶の世界のコーナーの展示物に関するものが、一番多い。質問に対して適切に対応できるよう、今後も努力してゆきたい。 ③ 12の分野に分けて収集、整理、保存し活用をはかっている。民俗資料は広いスペースが必要なので、寄贈の申出があった段階で、保存状態、既に収蔵している資料との重複を事前調査し、無制限に増えない努力をしている。施設面としては、建設当初から収蔵庫は増設可能な設計となっている。 ④ 豊かな発想や大胆な仮設を立てて研究す事は重要な視点だが、空理空論に陥らないように、真実を明らかにし、科学的立証に基づいた実証主義に徹することが大切と考えている。 ⑤ 各業務で、各学芸員の考えや技能は充分に発揮されていると思っている。今後も、より発揮できる環境作りを進める。 ⑥ 教育的配慮のもとに、市民生活の文化的向上に役立つもので無くてはならない。研究成果は、市民に還元されている。小・中学校の学校教育支援講座として、学芸員が直接学校に出向き、授業を行っている。 ⑦ 社会教育施設なので、学習意欲を持った方が多く来館される。出来るだけ答えられるよう、誠実に対応している。幅広い層との、情報収集の機会であると捉えている。 ⑧ 金子村の地方自治、織物業や茶業、人物的には、繁田武平、粕谷義三、石川幾太郎、市村高彦、学習活動として、豊岡大学等が良い研究対象である。入間の近代化を総体的に捉えた研究はまだ進んでいない。今後さらに調査研究を進め成果を発表したい。 |
目次へ戻るにはブラウザの戻りボタン、または↓のリンクをクリックしてください。